最近、ストレスを感じている人がますます増えてきました。
厚生労働省の調査によると、「仕事や職業生活に関して強い不安や悩み、ストレスを感じている」と答えた労働者の割合は、過去5年間で顕著に増加しています。
- 2019年:58.0%
- 2020年:54.2%
- 2021年:53.3%
- 2022年:61.5%
- 2023年:82.7%
特に2023年の82.7%という数値は過去最高であり、主に30代~50代の働き盛り世代に集中していると言われています。
背景には、長時間労働や人間関係の複雑化、リモートワークを含む働き方の多様化など、さまざまな要因があります。こうした要因が重なり合うことで、身体や心のパフォーマンスが落ちやすくなっているのです。
※本記事のデータは、厚生労働省「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)」に基づいています。
■ ストレスが組織にもたらす“静かなダメージ”
ストレスは、個人だけの問題ではありません。
職場やチーム全体の雰囲気や成果にも、静かに影響を及ぼします。
たとえば、疲労や不安を抱える人が増えると、報告・連絡・相談の質が下がり、小さな誤解が対人トラブルへと発展することもあります。
人との距離感に悩み、余計に気を遣うようになり、チーム全体の活気が失われていく……そんな悪循環に陥ってしまうことも。
このような状態が続くと、離職やメンタル不調といった“目に見える問題”の前に、「やりがいの喪失」や「静かな孤立」といったサインが現れることもあります。
■ ストレスマネジメントにおける「第三者視点」の重要性
こうした状況を受けて、多くの企業がメンタルヘルス対策に力を入れています。
しかし現場では、「誰に相談すればいいか分からない」「相談されても、どう対応していいか分からない」といった声が少なくありません。
ストレスを感じているとき、人はつい「一人でなんとかしよう」としてしまいがちです。
けれど、そんなときこそ必要なのは“客観的な視点”です。自分ひとりで抱え込むと、思考が堂々巡りになりやすいのです。
また、睡眠不足・食欲不振・やる気の低下などの身体の変化にも、ストレスが隠れていることは少なくありません。
そうした状況に気づき、寄り添ってくれる誰かの存在はとても大きな支えになります。
人間関係が密な環境だからこそ、そうした役割を担える人が一人でもいるだけで、組織やチームがより健全に機能し、成長できる可能性が広がります。
■ パフォーマンス向上に不可欠な「ストレス対応力」
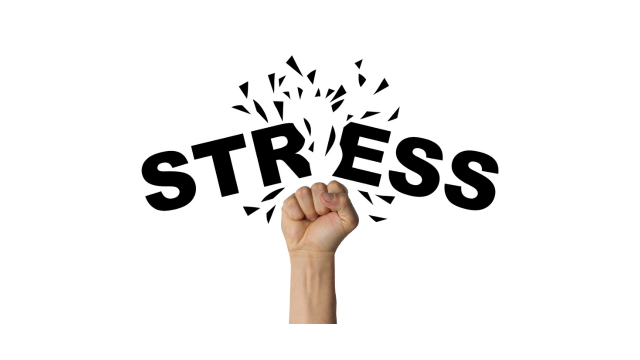
ストレスを理解し、適切に関わるスキルは、ビジネスの現場だけでなく、フィットネス指導やコーチングの現場でも非常に大切です。
たとえば、人がトレーニングに集中できない背景に、「仕事や家庭のストレスによる睡眠不足」が潜んでいることはよくあります。
このとき、ただ運動指導をするだけではうまくいかず、信頼関係の中で「本音」を引き出し、メンタル面をサポートできる力が問われます。
もし、職場や現場に「相手の変化に気づき、声をかけられる人」が一人でもいれば、チーム全体の雰囲気や成果は大きく変わってきます。
- 「最近、様子がちょっと違うな」と気づける
- 「無理してない?」とさりげなく声をかけられる
- 「よかったら話してみない?」と自然に伝えられる
こうした一言が、個人のパフォーマンスだけでなく、チーム全体の力を引き出すきっかけになるのです。
ストレスをゼロにすることはできません。だからこそ、「対話できるトレーナー」の存在が、これからますます求められていきます。
■ 「ストレスリリーフスペシャリスト」という選択肢
今、フィットネスの現場や企業の中で、「ストレスに気づき、対話を通じて支えられる人材」が求められています。
NESTAの「ストレスリリーフ スペシャリスト」は、そうした役割を担える“相談できる専門人材”として、あなたの成長を支えてくれる資格です。
あなた自身が、誰かにとっての支えになる存在になってみませんか?
関連資格のご案内
ストレスに気づき、対話を通じて支えられる人材になるため「呼吸法やメディテーション(瞑想)、ストレッチ、カウンセリングなどの知識」を深めるために、以下の資格取得をおすすめします:
- 糖尿病予防スペシャリスト:ストレス軽減で糖尿病リスクをコントロール
詳細は、NESTA Japan公式サイトをご覧ください。



